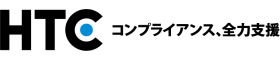神戸新交通で拾得金を不適切保管 約5万4千円
2025年8月、神戸新交通は、駅や車両で見つかった拾得金の一部を、警察へ届けずに保管するなどの不適切な対応があったことを発表した。
同社の規程では、拾得物や拾得金は、台帳に記載した上で拾得してから原則1週間で警察に届け出ることになっていた。50円~500円玉などは規程通りに届けられていたが、1円~10円玉などの少額の硬貨の一部が駅や事務所で保管されていたという。保管金の総額は約5万4千円で、一部は消耗品の購入に使われていた。
【このニュースに一言】
1円や10円といった少額硬貨では、持ち主が現れる可能性は極めて低く、警察への届け出や台帳記載は現場にとって手間のかかる作業です。駅や事務所の担当者からすれば、「業務に追われる中で、この手間は正直負担だ」という感覚は理解できます。実際、こうした現実的な事情から、長年にわたって慣習化してしまった面もあるのでしょう。
しかし、「少額だから」「面倒だから」という理由で規程違反を例外として認めてしまえば、その“例外”はやがて広がります。たとえば「少額の経費だから」「一時的な流用だから」という発想が芽生えれば、規律は緩み、やがて大きな不正につながる可能性があります。実際、多くの不正は“小さな違反の見逃し”から始まっています。
組織にとって大切なのは、違反の大小よりも「ルールを守る姿勢」です。外から見れば、“小さなことでもルールを守る組織”は、それだけで誠実さや信頼感を与えます。そして、そのような組織では、より大きなリスクの芽を早期に摘み取ることができます。
だからこそ、今回の事案は単なる“硬貨の扱い方”の話ではありません。日々の小さな行動が、組織の信頼を守るか損ねるかの土台になることを、改めて意識する必要があります。