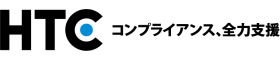パワハラって言われたくない!どんな指導をしたらいい?
「パワハラと言われるのが怖い」と、指導をためらった経験はありませんか。部下にパワハラと受け取られない指導のポイントは、場所と伝え方にあります。ハラスメントについて研究している社会疫学者の津野香奈美・神奈川県立保健福祉大学大学院教授は、著書『パワハラ上司を科学する』の中で、パワハラと受け取られない指導を行うための鉄則として、以下の3点を提言しています。(表現は少しアレンジしています)
1.周りに人がいない状態で行う
2.先によいところ・できているところをほめる
3.どの言動を、どのような理由で、どう改善してほしいのかを具体的に伝える
指導内容は適切であっても、周りに人がいる状態だと部下は「恥をかかされた。これはパワハラだ」と思うかもしれません。人前での指導が、ただちにパワハラとなるわけではありませんが、部下の気持ちに配慮して、指導はなるべく1対1で行いましょう。
また、伝える順番もたいせつです。最初に指摘から入ると、部下は「責められている」と認識し、聞く耳を持たなくなったり反論してきたりすることも考えられます。まずは、よいところ・できているところを伝え(たとえば「いつも面倒な作業を引き受けてくれてありがとう。とても助かっています」など)、ワンクッション置いてから指摘や指導に入りましょう。部下の警戒心が和らぎ、話を聞いてもらいやすくなります。
そして、もっとも重要なのは3つめのポイントです。問題点や指導の理由を明確に伝えずに非難するだけでは、部下は何が問題なのかがわからず理不尽さを感じてしまいます。指導の前に「どの言動を、どのような理由で、どう改善してほしいのか」を整理しておきましょう。たとえば、書類の提出期限を守らない部下に指導を行うときは、
「書類の提出が遅れがちなことが気になります。提出期限を過ぎると、ほかの社員の業務も滞ってしまいます。遅れそうなときは、予定や業務分担を見直したいので、なるべく早く相談してもらえますか」
というような指導がよいでしょう。「使えないやつだな!」などと、相手の人間性や能力を否定することはNGです。問題となっている、具体的な言動のみに焦点を当てて指導しましょう。
パワハラには法的な定義もあり、「指導を受けた本人がパワハラと感じたから」という理由だけでパワハラになることはありません。だからといって、配慮のない指導で相手を傷つけ、モチベーションを低下させることは、だれのためにもなりません。冒頭の1~3のポイントを参考にして、よりよい職場環境をつくっていきましょう。
参考資料:『パワハラ上司を科学する』(津野香奈美・著 / ちくま新書 / 2023年)