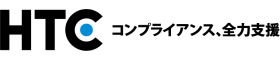偏見に囚われると、見えないものがある「イロメガネッコ」

「最近の若い子ってさあ、Z世代だかなんだか知らないけど、本当に根性がないよね」
居酒屋で飲んでいると、後ろの席から、そんな話し声が聞こえてきた。どうやら、新卒就職者の離職率が高いというニュースで盛り上がっているようだ。思わずそちらを見ると、やはり、いる。客たちには見えていないようだが、彼らの頭や肩の上を、あの生物が這い回っている。
数年前
かつての私は、偏見の強い人間だった。年齢や性別、出身地や学歴などで人を決め付け、色分けしていた。不動産会社の営業職として、思い通りに次々と成約を決め、自分の考え方は的確で間違いないと、思い込んでいた。
新入社員
ある日、私のいる営業所に葛西という新入社員が配属された。新卒の彼は当然「若者」であり、「一流大学出身」でもなかった。また、配属初日に葛西の挨拶の声が少し小さいと感じたことや、当時の私の感覚として「ちゃらちゃらしている」見た目であったことから、私は彼を「この仕事に向かない」「どうせすぐに辞める」と、決め付けていた。
しかし、すぐに私は彼の働きぶりに驚かされることになった。営業は困難な依頼やクレーム対応などあり、一筋縄ではいかない。経験もなく知識も少ない新入社員には、よほど優秀でない限り、体力、精神ともにきついと感じることばかりだろう。だが、彼はとにかく粘り強く一所懸命で、責任を持って仕事に取り組んだ。また、失敗してもくじけることなく、気持ちを切り替え、次の行動に着手する。倒れてもすぐに起き上がる彼の姿は、まるで起き上がりこぼしのようだ。私は感心し、葛西という新入社員への偏見は、霧散した。
女性上司
葛西が配属された少し後に、上司が異動で替わった。新しい上司の小岩課長は女性で、保育園児、小学二年のこども二人を育てながら働いていた。私はまた葛西のときと同様に彼女を決め付け、不信感を持った。
「組織をまとめるのは男性がふさわしい。幼いこどもがいるならなおさらだ。どうせ家庭の事情とかで頻繁に休んで、俺たちに負担がかかる」と。
しかし、その後の流れは、ご想像の通りである。小岩課長は強いリーダーシップで部署を率い、結果を出していた。時折、私が危惧したような家庭の事情で急遽休むこともあったが、用意周到で、そのリカバーも迅速かつ的確。文句を言う隙もなく、育児と仕事を見事に両立させていた。
その年、私たちの営業所は、全営業所の中でトップの成績を残した。それは葛西と小岩課長の活躍が大きかったと、私を含め営業所の誰もが認めた。
例外
二人と出会ってから、私には変化が起きていた。「最近の若者は…」「女は…」と、以前なら自然と口に出ていた偏見を口にしようとすると、脳裏に葛西と小岩課長という「例外」が浮かび、言い淀んでしまう。また同時に、ぐらりと頭が揺れる感覚もあった。そのようなことが続いた結果、ついに私の考えは偏っていることを自覚した。加えて、平然と偏見を口にしていた自分自身が、なんとも惨めで恥ずかしく思えた。
自覚
その途端、頭が軽くなった。それは気分的なものだけではない。小動物くらいの重さの何かが、すとんと頭上から降りたのだ。気配がする方向に目をやり、私はぎょっとした。とげとげしい毛並みで猫のような生物がいたのだ。その生物は私を一瞥すると、足早に走り去ってしまった。それが「イロメガネッコ」という、人の持つ偏見を増幅し、色眼鏡で物を見てしまうこんぷらモンスターだったと知ったのは、少し後のことだった。
それから私は、何かと決め付けそうになったときは、「偏見かもしれない」と考えるようになった。いなくなったように見えてもイロメガネッコは、まだ私の中にいるかもしれない。
偏見を完全に捨て去るのは難しい。しかし、偏見があると自覚することなら、できるはずだ。
(証言者 元不動産会社 営業部A)
※この物語はフィクションです。実在の人物・団体・事件などには一切関係ありません。