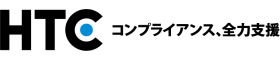背後に感じる視線、その正体は闇の中「ギョウシー」

同期入社の経理担当者が、「処理する数が多過ぎて、正直、内容なんて細かくは見ていない」と嘆くのを聞いたことがあった。それはつまり、プライベートの領収書を、交際費として簡単に通せるということではないか。手元には、昨夜ハメを外し過ぎて、生活に大打撃を与えるくらいの金額になった領収書がある。これがチャラになるなら…という考えがよぎる。そのとき、背後に視線を感じた。同僚はすでに皆帰宅し、部署内には私一人のはずなのに…。恐る恐る振り返ると、それはいた。
見られている
黒い何かが、物陰からこちらを覗いている。はじめは、何かの影かと思った。しかし、ぎょろりとした大きな目と目が合い、それが生き物であることがわかった。大きな瞳が、じっと、私を見つめ続ける。すぐにでも目をそらしたいのに、金縛りにあったかのように身体が動かない。底知れない穴のように深く黒い瞳に、心の奥までを全て見透かされているような気分になる。それなのになぜか、恐怖の感情はなく、不気味だった。目が合って何秒、いや何分経過したのか、わからない。心臓の鼓動がうるさいくらいの静寂の中、気付く。そうか、目をそらせないなら、瞑ればいい。
まぼろし
目を瞑れば、何も見えない。そのはずだった。しかし、視界には、私の両親が立っていた。実家にはしばらく帰っていないが、記憶の中の両親そのままの姿だ。二人は悲しそうな表情で私を見つめ、話しかけてくる。
「馬鹿なことは、やめて」
「お金に困っているなら、相談しろ」
そう言って懐から財布を取り出す父の様子に、居たたまれない気持ちがこみ上げてくる。そして今度は誰かの声が頭上から聞こえてきた。
「本当にやるのか?」
「人生を台無しにするのか?」
両親の姿もこの声も、幻覚・幻聴、まぼろしだ。そんなことはわかっているのに、冷静ではいられない。一度くらい。会社にとってはたいした額じゃない。絶対にバレない。私は言い訳をするように、心の中で唱える。
すると、それをかき消すようにひときわ大きな声が響き渡った。
「お前がやろうとしていることは、犯罪だ」
私は目を開けた。
目が覚める
視界にはいつも通りのオフィスが広がる。やっと、まぼろしから解放されたようだ。しかし、手元の領収書に視線を落とすと、先ほどまでの光景、音が、脳裏に張り付いてくる。全てを見透かすような視線。両親の表情。謎の声…。これらの意味を、ようやく悟った。
この領収書は、犯罪者への片道切符でしかない。私は頷き、迷わずシュレッダーにかけた。
あれはなんだったのか?
これが、私が人生で一度だけ、不正会計を行いかけたときの話だ。今思うと、あの謎の生物はこんぷらモンスターだったのかもしれない。モンスターというと、不正を行う「悪い」イメージが、世間に根付いている。私にとっての認識もそうだった。しかし、なかには、不正を制止したり、善行をしたりする「良い」モンスターも存在するらしい。あの生物を見て「怖い」と思わなかったのは、危害を加えられないことを本能的に感じ取ったからなのかもしれない。
あの生物は、幻覚や幻聴を操り、不正に染まりかけた私の手を止めてくれたのではないだろうか? そして、あのとき、私を一喝した声は、実は私自身の声ではなかっただろうか?
真相はわからない。それでも、私にはそう思えてならない。
(証言者 証言者 卸売業の営業課長代理A)
※この物語はフィクションです。実在の人物・団体・事件などには一切関係ありません。